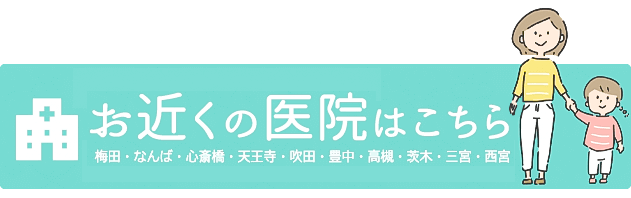裏側矯正は歯磨きがしにくいことから、歯肉炎になりやすいというデメリットがあります。裏側矯正治療中の歯肉炎の予防は歯ブラシだけでなくタフトブラシと歯間ブラシを使ってセルフケアすることです。それぞれご説明します。
目次
裏側矯正で歯肉炎を起こしやすいわけ

矯正装置がついている歯は、何も付いてない歯に比べると汚れがたまりやすくなります。裏側矯正の場合は、歯に小さくデコボコした形状の矯正装置とワイヤーを歯の裏側につけるため、汚れがつきやすく落としにくいということになり、毎日歯磨きをしていてもどうしても食べカスが残って歯垢になってしまいます。
歯垢は細菌の塊ですので、虫歯や歯周病を起こしやすい状態になり、虫歯で歯に穴が開いたり、歯肉炎になったりするリスクが高まります。歯肉炎に一度かかったら、丁寧に歯磨きをしてお口の中の細菌を減らすことで、少しずつ歯茎の状態が改善していきます。
歯肉炎とは?
歯肉炎の代表的な症状は、歯茎が赤く腫れる、歯磨きをするときに歯ぐきから血が出るというものです。歯磨きの仕方によっては歯肉炎を起こしていても歯ぐきからの出血がなく、歯肉炎にかかっていることに気づかない場合もあります。
また、歯肉炎に気づかなかったり、少しの出血なら大丈夫だろうと放置すると、歯肉炎が悪化して歯周炎となり、歯周病の本格的な治療が必要になります。
裏側矯正中に歯肉炎が起こりやすい理由
裏側矯正では、装置が歯の裏側に装着されるため、以下の理由で歯肉炎のリスクが高まります。
- 清掃の難しさ・・装置が歯の裏側にあることで、歯ブラシが届きにくく、歯垢が溜まりやすくなります。
- 歯垢の蓄積・・装置の周囲に歯垢が溜まりやすく、適切に除去しないと歯肉炎の原因となります。
- 唾液の流れの変化・・装置が唾液の流れを妨げることで、口腔内の自浄作用が低下し、細菌の増殖を促進します。
歯肉炎の原因は歯垢がついていること
歯肉炎の原因になるのは歯垢(プラーク)です。食べカスなどが歯について2日程度たつと歯垢が出来ます。歯垢は細菌の塊なので、細菌の出す毒素によって歯茎が刺激を受けて炎症を起こして赤く腫れている状態が歯肉炎です。
歯垢がきれいに除去出来ていてお口の中に溜まることがなければ、歯肉炎は殆ど起こりません。そのため、歯肉炎から歯や歯茎を守るためには、しっかりとブラッシングして歯垢を出来るだけ除去することが大切です。
裏側矯正で歯肉炎になるのはメンテナンス不足

裏側矯正装置は構造上、歯肉炎になりやすいため、装置をつける前に歯ブラシ指導を行うことがあります。歯の裏側の状態を確認するために、デンタルミラーと呼ばれる小さな鏡を見ながら歯みがきします。
装置をつけた後は、必ずデンタルミラーで歯の裏側の状態を確認しながら歯磨きしなければなりません。歯肉炎の予防のためには、歯ブラシの他、タフトブラシと歯間ブラシを使用でする事をおすすめします。
裏側矯正中の歯磨きの仕方
まず、用意して頂きたいのが、ヘッドが小さめのやわらかめの歯ブラシと、タフトブラシ、歯間ブラシの3つです。
裏側矯正装置を歯に付けた後は、歯ブラシを普通に当てた状態では汚れがあまり落ちません。矯正装置や歯についた汚れを効果的に落とすには、歯ブラシを角度をつけた状態で当てることが大切です。
奥歯の噛む面や装置の付いていない面は、いつも通りの歯ブラシの当て方でしっかりと磨きましょう。しかしあまり強く歯ブラシを当てすぎると装置が取れてしまいますので、歯の裏側をブラッシングする時には、いろんな角度から歯ブラシを小さく動かしながら当てましょう。
その後、タフトブラシに持ち替えて矯正装置のデコボコした部分をきれいにしていきます。タフトブラシは先が小さく、通常の歯ブラシよりも色々な角度からピンポイントで歯に当てることが出来ます。
タフトブラシを使う時は、歯を1本1本ていねいに磨いていきます。歯と歯の間や歯と歯茎の際のところは、特に丁寧に磨きましょう。
歯と歯の間は通常ならデンタルフロスを通すのが効果的ですが、裏側矯正ではワイヤーが通っているため、歯と歯の間にフロスを通すことが出来ません。
そのため、裏側矯正治療中は歯間ブラシを使います。歯間ブラシは様々なサイズがありますので、メンテナンスの時にぴったりのサイズを歯科衛生士に選んでもらいましょう。
歯肉炎を予防するためには、日常の口腔ケアが非常に重要です。以下のポイントを参考にしてください。
適切な歯磨きの実践
-
歯ブラシの選択・・矯正用の歯ブラシやタフトブラシを使用し、装置の周囲や歯と歯茎の境目を丁寧に磨きます。
-
歯磨きのタイミング・・食後すぐに歯磨きを行い、歯垢の形成を最小限に抑えましょう。
-
歯磨き粉の選択・・フッ素配合の歯磨き粉を使用することで、虫歯予防にも効果的です。
補助清掃器具の活用
-
歯間ブラシやデンタルフロス・・歯と歯の間や装置の下など、通常の歯ブラシでは届きにくい部分の清掃に役立ちます。
-
マウスウォッシュの使用・・抗菌作用のある洗口液を使用することで、口腔内の細菌数を減らすことができます。
これらのセルフケアを継続することで、歯肉炎の予防に大きく貢献します。
食生活と生活習慣の見直し
日常の食生活や生活習慣も、歯肉炎の予防に影響を与えます。以下の点に注意しましょう。
-
バランスの取れた食事・・ビタミンCやカルシウムを豊富に含む食品を積極的に摂取し、歯茎の健康をサポートします。
-
間食の制限・・頻繁な間食は歯垢の蓄積を促進するため、控えるよう心掛けましょう。
-
禁煙と節酒・・喫煙は歯茎の血流を悪化させ、飲酒は口腔内の乾燥を引き起こすため、歯肉炎のリスクを高めます。可能な限り控えることが望ましいです。
これらの生活習慣の見直しは、口腔内の健康維持に大きく寄与します。
食生活と生活習慣の見直し
日常の食生活や生活習慣も、歯肉炎の予防に影響を与えます。以下の点に注意しましょう。
-
バランスの取れた食事・・ビタミンCやカルシウムを豊富に含む食品を積極的に摂取し、歯茎の健康をサポートします。
-
間食の制限・・頻繁な間食は歯垢の蓄積を促進するため、控えるよう心掛けましょう。
-
禁煙と節酒・・喫煙は歯茎の血流を悪化させ、飲酒は口腔内の乾燥を引き起こすため、歯肉炎のリスクを高めます。可能な限り控えることが望ましいです。
これらの生活習慣の見直しは、口腔内の健康維持に大きく寄与します。
定期的な歯科健診とクリーニングの重要性
裏側矯正中は、セルフケアだけでは十分な歯垢除去が難しいため、歯科医院での健診とクリーニングを受けることが重要です。
定期健診の頻度
- 裏側矯正中は、通常の歯科健診よりも頻繁に通院することが推奨されます。
- 目安として、1〜2ヶ月に1回は歯科医院でクリーニングを受けると良いでしょう。
歯科医院でのクリーニング
- 専用の器具を使い、歯垢や歯石を徹底的に除去してもらいます。
- 歯科衛生士による指導を受けることで、適切なセルフケアの方法を学ぶこともできます。
フッ素塗布や抗菌ジェルの活用
- フッ素塗布を行うことで、歯の表面を強化し、虫歯や歯肉炎を防ぐことができます。
- 必要に応じて、抗菌ジェルや歯肉の炎症を抑える薬剤を処方してもらうのも効果的です。
歯科医院での定期的なチェックとクリーニングを組み合わせることで、裏側矯正中でも健康な歯茎を維持しやすくなります。
まとめ

裏側矯正中の歯磨きは、装置をつけていない時と比べると手間のかかるものですが、歯肉炎を防いで歯茎を健康な状態に保つには、欠かせないものです。歯肉炎が悪化すると、一時的に矯正治療を中断する場合もありますので、出来るだけきれいなお口を保ちましょう。もし、矯正治療中に歯茎や歯について気になることがあれば、なんでも歯科医院にご相談下さい。
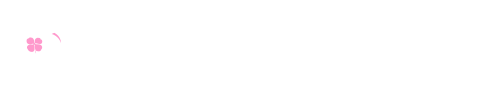
 医療法人真摯会
医療法人真摯会