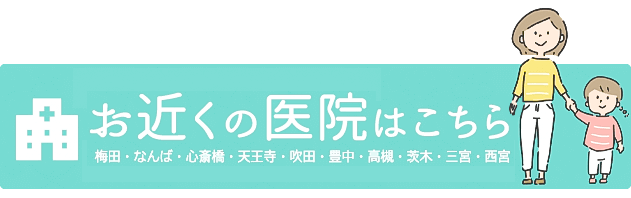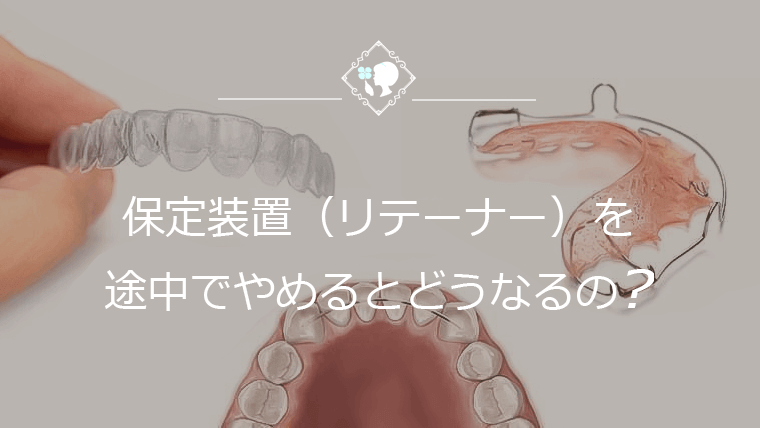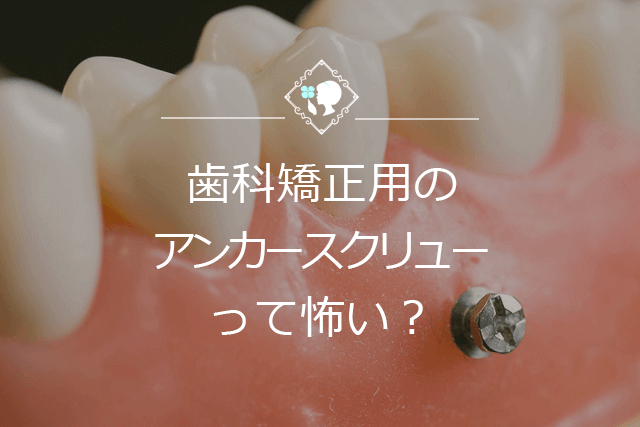矯正治療は装置を装着するので、お口の中の清掃が難しくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。治療中の歯磨きの重要性と、効果的なケア方法についてご説明します。
矯正治療中の口腔環境の変化
 装置を装着することで、患者さんのお口の中には以下のようなさまざまな変化が生じます。これらの変化を理解し、適切なケアを行うことが、矯正治療中の健康な口腔環境を保つポイントとなります。
装置を装着することで、患者さんのお口の中には以下のようなさまざまな変化が生じます。これらの変化を理解し、適切なケアを行うことが、矯正治療中の健康な口腔環境を保つポイントとなります。
1. 歯垢がたまりやすくなる
装置(ブラケットやワイヤー、バンドなど)をつけると、歯の表面が複雑な状態になり、その結果プラークが溜まりやすくなります。
- 食べ物のカスが残りやすい・・食事の際に、装置の隙間や周囲に食べ物が挟まることが多くなります。
- 歯磨きがしにくくなる・・通常よりも時間をかけて、丁寧に装置の周りを磨く必要があります。
- 細菌が増える・・残った汚れが細菌の栄養源となり、虫歯や歯肉炎のリスクを高めます。
2. 歯肉炎や歯周病のリスクが高まる
歯垢をそのまま放置すると、歯肉が赤く腫れる状態(歯肉炎)が発生しやすくなります。装置を装着していると、全体的にブラッシングが難しくなるため、炎症が進行する可能性もあります。
- 歯肉炎の症状・・歯肉の腫れ、赤み、出血(特に歯磨き中)が見られることがあります。
- 歯周病への進行・・炎症が歯周ポケットに広がると、歯周病になり、最悪の場合、歯を支える骨の吸収が起こることもあります。
3. 装置が唾液の流れを妨げる
装置が装着されると、装置が物理的に唾液の流れを妨げることがあります。また、装置の存在により口腔内が違和感を感じやすく、無意識に唾液の分泌量が変化する場合があります。
唾液の役割
唾液には抗菌作用や自浄作用があり、口腔内を健康に保つために重要です。
唾液分泌の減少によるリスク
唾液量が減ると、食べ物のカスや細菌を洗い流す能力が低下します。その結果、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
4. 口臭の発生リスク
矯正装置に残った食物残渣や歯垢が分解される過程で、口臭を引き起こすことがあります。特に清掃が行き届かない場合、悪臭の原因となる硫化水素などのガスが発生することがあります。
口臭の原因物質
口臭の主な原因は、口腔内の細菌が食物の残りや歯垢を分解することで生じるガスです。
口臭の予防法
毎日の丁寧な歯磨きや、デンタルフロス・歯間ブラシの使用が効果的です。また、マウスウォッシュの使用も口臭予防に役立ちます。
5. 装置の種類による影響の違い
矯正治療で使用する装置には、固定式(ワイヤー矯正、裏側矯正)と取り外し式(マウスピース型矯正 例:インビザライン)の2種類があります。固定式と取り外し式では口腔環境への影響が異なります。
固定式装置
ブラケットとワイヤーを取り付けるため、凹凸があって歯磨きが難しくなります。凹凸に汚れがたまるので、ブラッシングをしても汚れが残りやすく、プラークがたまってしまい、歯肉炎のリスクが高くなります。
取り外し式装置
取り外しのできるマウスピース型の装置の場合は、外して普段通りに歯磨きが出来ます。ただし、表面にアタッチメントがついている場所については、丁寧にブラッシングする必要があります。固定式に比べて歯磨きがしやすいですが、装置の装着時間を守る必要があります。
6. 装置の圧力による歯の移動とその影響
矯正装置の圧力によって歯が移動する過程で、歯周組織にも負荷がかかります。この負荷によって敏感になり、痛みや腫れが起こることがあります。
- 歯茎の痛みや腫れ・・歯が動く際には軽い痛みや腫れを感じることがありますが、これは一時的なものです。
- 歯磨きを丁寧に行う・・痛みや腫れが続く場合は、丁寧にブラッシングを行い、必要であれば担当医に相談しましょう。
歯磨きの重要性

矯正を始めると、装置によってセルフケアが難しくなると感じる患者さんも多いのではないでしょうか?しかし、治療中の歯磨きを疎かにすると、むしろ逆効果になってしまうこともあります。
なぜ矯正治療中の歯磨きが重要なの?
治療中のお口の中は、通常よりも汚れが溜まりやすい状態になっています。
矯正装置が歯垢を溜まりやすくする
ワイヤー矯正でもマウスピース矯正でも、装置があることで表面に汚れが付きやすくなります。特にブラケットやワイヤーの隙間は、食べカスやプラークが残りやすく、放置するとむし歯や歯周病のリスクが高まります。
歯肉炎になりやすい
汚れが溜まると歯ぐきが炎症を起こしやすくなり、腫れや出血が生じることがあります。これを放置すると、歯周病へと進行する可能性もあるので、気をつけなければいけません。
口臭の原因にもなる
治療中に歯磨きが十分に出来ていないと、汚れが残ってしまって口臭の原因になることがあります。特にワイヤー矯正では、装置に食べカスが詰まりやすいため、食後の歯磨きが必須です。
効果的な歯磨き方法は?
では、矯正治療中にどのようなセルフケアをすればよいのでしょうか?ここでは、装置ごとの歯磨きのポイントをご紹介します。
ワイヤー矯正の場合
- 矯正用のブラシを使う → 通常の歯ブラシでは届きにくい部分があるため、専用のブラシを使用すると効果的です。
- 歯とワイヤーの隙間を意識して磨く → 装置の周りにはプラークが溜まりやすいため、細かい部分まで丁寧に磨くことが大切です。
- タフトブラシで仕上げ磨きをする → 小さなヘッドのタフトブラシを使うことで、ワイヤー周りや歯間をきれいにできます。
- デンタルフロスや歯間ブラシを活用する → ワイヤーが邪魔をして通常のデンタルフロスが使いにくい場合は、矯正専用のフロスや歯間ブラシを取り入れると良いでしょう。
マウスピース矯正(インビザライン)の場合
- マウスピースを外して歯を磨く → マウスピース矯正では、装置を外してからしっかりと歯磨きをすることが可能です。
- マウスピース自体の清掃も忘れずに → マウスピースに汚れや細菌が付着すると、口臭やむし歯の原因になります。専用の洗浄剤を使うのもおすすめです。
- 食後は必ず歯磨きをする → 食事後に歯磨きをせずにマウスピースを装着すると、むし歯のリスクが高まります。必ずブラッシングしてから装着しましょう。
装置をつけている場合、以下のポイントに注意して歯磨きを行いましょう。
- 歯ブラシの選択 → ヘッドが小さく、毛先が細いブラシを選びます。
- あてる角度 → 歯茎の縁に45度の角度で当て、小刻みに動かします。
- 装置周辺の清掃 → ブラケットやワイヤーの上下を丁寧に磨きます。
- 歯間をきれいにする → 歯間ブラシやデンタルフロスを使用して、歯間を清掃します。
細菌は唾液の分泌が減少する夜間に繁殖しやすいため、特に就寝前の歯磨きは念入りに行いましょう。
歯磨きに役立つツールの紹介

矯正治療中の口腔ケアを効果的に行うために、以下のツールを活用しましょう。
- タフトブラシ → ヘッドが小さく、細かい部分の清掃に適しています。
- 歯間ブラシ → 歯間や装置の隙間の汚れを効果的に取り除きます。
- デンタルフロス → 歯間に通して使うため、プラークの除去に効果的です。
- マウスウォッシュ → 歯磨き後の仕上げとして、口腔内の細菌を洗い流して減少させます。
これらのツールを組み合わせて使用することで、より徹底した口腔ケアが可能となります。
食生活と口腔ケアの関係
矯正治療中は、食生活にも注意が必要です。
- 粘着性の高い食品 → キャラメルやガムなどは装置に付着しやすいため、控えましょう。
- 硬い食品 → ナッツや硬いキャンディーは装置を破損する可能性があるため、避けましょう。
- 糖分の多い食品 → 虫歯のリスクを高めるため、摂取を控えましょう。
バランスの良い食事と適切な口腔ケアを組み合わせることで、矯正治療の効果を高めることができます。
定期健診の重要性

矯正治療中は、定期的な健診が不可欠です。
- 装置の調整 → 適切な力で歯を動かすために、定期的な調整が必要です。
- 口腔内のチェック → 虫歯や歯周病の早期発見・治療が可能です。
- プロによるクリーニング → 医院でのクリーニングでは、自宅で取り切れない汚れを専門的に除去することが出来ます。
- 治療計画の確認 → 治療が計画通りに進んでいるかを確認し、必要に応じて計画を調整します。
患者さん自身が日々のケアを行うことに加え、医院での健診を定期的に受けることで、矯正治療を安全かつ効果的に進めることができます。
まとめ
矯正治療中は、装置の影響で口腔内にプラークや食べ物のカスが溜まりやすい環境になります。そのため、毎日の丁寧な歯磨きが必要です。
また、食生活にも気を配り、粘着性や硬い食品を控えることも効果的です。患者さんご自身のケアと定期健診でのクリーニングによって大切にケアしながら健康な口腔環境を維持し、矯正治療を進められます。
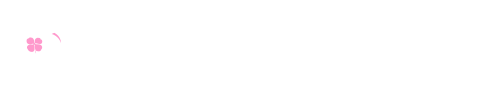
 医療法人真摯会
医療法人真摯会